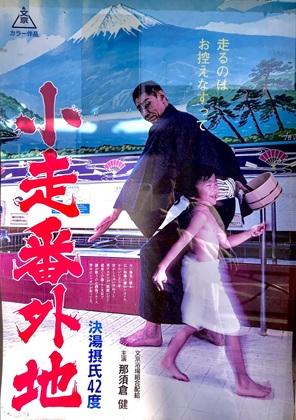同タイトルの公開講座が東京大学で行われ、その初日に参加してきた。印象に残った講演から引用し、考えてみたい。
それは、“現代社会に対するハンナ・アーレントの警告”という題で、彼女の著作である、政治における嘘を扱った『真理と政治』の読解を中心に進められた。
前段として、政治の嘘に係わる人の態度として、「嘘の理論を心から信じるわけでもなく、理論が嘘と知りつつそれを必死に隠そうともしない」人を挙げている。言い換えると、<嘘に基づいて政策実行することの意味が分かっているがやっている>態度と、<政策実行をしているがそれが嘘に基づいていることがわかっていない>という二つの態度の差が実はなくなっている、ということだそうだ。
よくわからないところがあるが、なぜ、そんなことになるのか?という疑問が湧いてくる。官僚の意識が曇ってきているのか、政治は誰がトップになろうと…、どうやろうと、世の中は変わらない、という諦めの心境を持つ人が増えているのか?
アーレントは、現代の政治的嘘を分析するために、何とソクラテスに言及している。アーレントは、「思考」の定義をプラトンの対話編『ゴルギアス』でのソクラテスの台詞―「ぼくがぼく自身と不調和であること」という文言だけから導き出す。
自分がやっていることと矛盾する事実やデータに気付いた人間は、「お前がやっていることは、この事実やデータと矛盾しているではないか」という内なる声を聞く。その声に対し、「本当に矛盾するだろうか。見てみよう。」とか、「確かにそうだ。こんなおかしなことはやめよう。ではどうやってやめようか」などといった内なる対話が始まるならば、その時こそ、その人間はものを考えている。これが、アーレントの考えた「思考」の定義だ。
アーレントは、最終的に、ひとつの命題にたどり着く。
「自分自身と不調和であり、自分自身に矛盾しているよりも、世の中全体と不調和の方がいい」
そして、「命題の真理は実際にそれをやって見せることによってのみ人びとに行為を鼓舞できる」、「われわれが勇気や善の行為をなそうとするときはいつでも、他の誰かを模倣している」とも言っている。
アーレントは「思考すること」が道徳的責任の前提だと考えたようである。「声なき対話」は、アーレントにとって思考そのものであり、しかもそれは「知識を生み出すため」ではなく、「自分自身と対話することで、責任を持って生きられるか」を確認する道徳的営みといえる。
人智学では、人間は「高次の自己」と「下位の自己(欲望や習慣にとらわれた自我)」のあいだで、常に対話している存在だとされる。アーレントがいう「わたしと私自身」とは、この二重の自己が出会う場と対応させることができる。これは、「自分自身と折り合う」と表現できる。「折り合う」とは、衝動や利己的な動きを抑えつけるのではなく、それらを意識に取り込み、霊的自己の光のもとで調和させることを意味する。
アーレントは「思考の欠如」が悪を招くと見たが、人智学も「生きた思考」こそ人間を霊的に目覚めさせ、自由な行為を生むと考える。つまり「折り合える自己」への道は、知識や規範や既成の道徳に従うのではなく、思考を通じて自由に行為することと同じだ。「何々しなければならない」という、いかなる外からの強制も、排除される。
ただし、自分の内で「本当に納得できないこと」をしてしまえば、それは必ず他者との関わりにゆがみを生じさせ、共同体全体に影響する。孤立した個人の内省ではなく、あくまで共同体の調和のためだ。「自分と折り合った」誠実な行為は、共同体の中で信頼や共鳴を生み、未来を軽やかにする。一人の人間が「自分との折り合い」を保つことで、その人の行為は他者に安心感を与え、共同体の中で「信頼の核」となりえる。
この講義は、政治の嘘から始まり、人間の内的自覚にまで及んだ、かなりシリアスな内容を扱ったものだったが、講師の先生は、直感的にみて、朗らかでユーモアたっぷりで、打ち解けやすい方だったと思う。東大の教授にしては…。それがなんだか救いになっているような気がした。